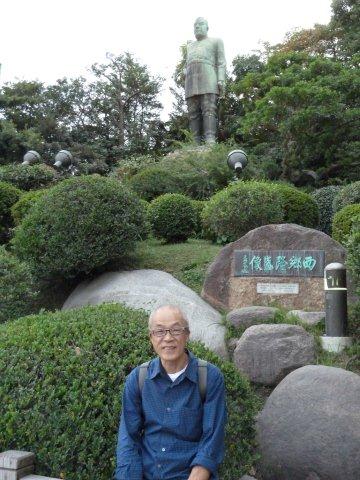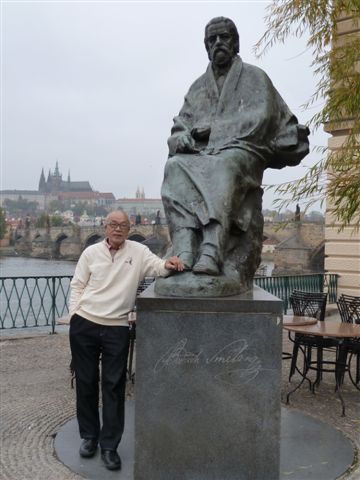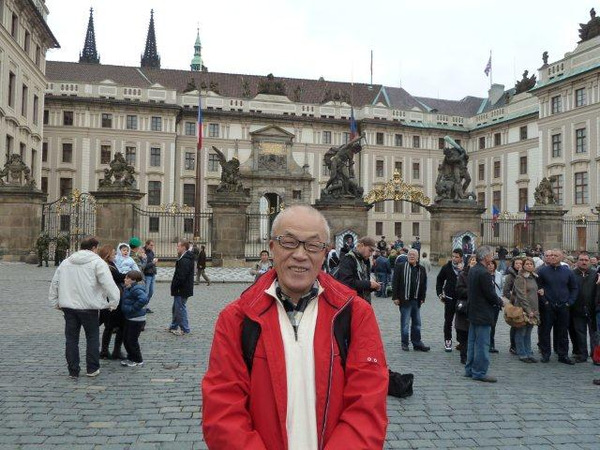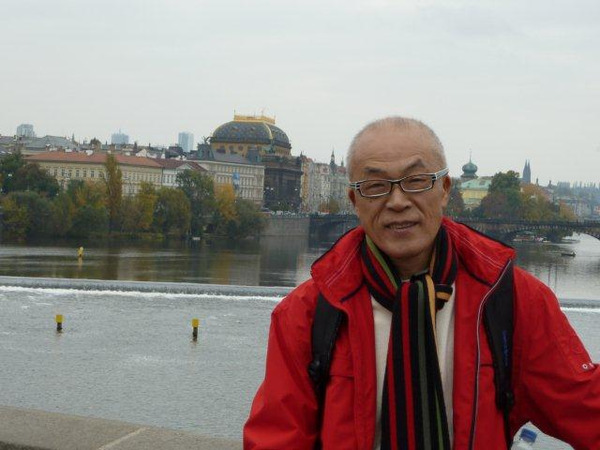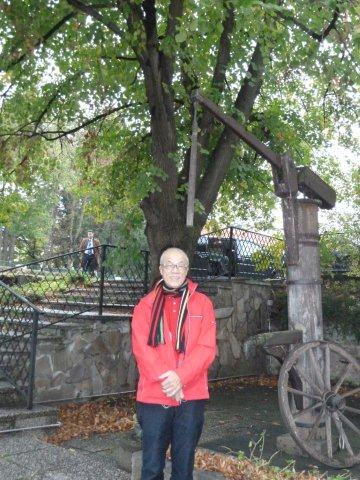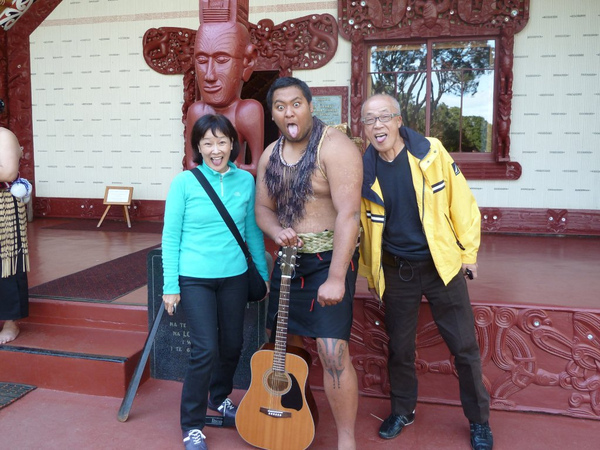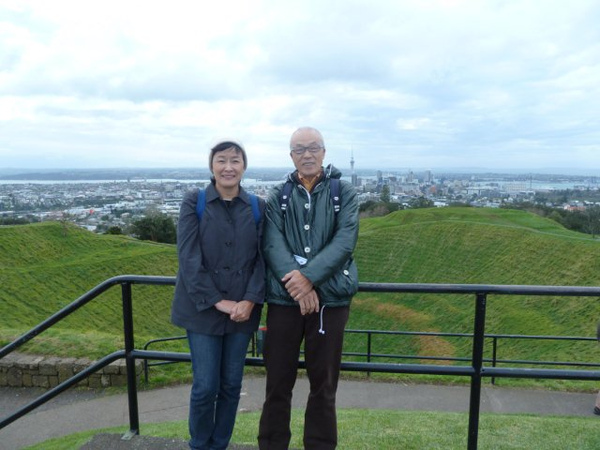2012年1月24日
長年あこがれていた冬の日本海。昨日から明日まで、2泊3日の予定で、ようやく実現することができました。「リゾートしらかみ」というJRの特急に乗って、秋田から鰺ヶ沢を経て、青森までという行程です。
この特急、なかなか予約が取れないので、今回はパック旅行にしました。本意ではないのですが、やむを得ません。23日の早朝に出発、上野から秋田までは新幹線。秋田で食事をして、14時10分発の特急で鰺ヶ沢着は17時18分です。3時間少々の旅ですが、やはり真冬の日本海沿いを走るのですから、迫力があります。雪こそ降っていませんでしたが、とにかく波のすごいこと。それだけ風が強いわけですが、海岸の岩にぶち当たって跳ね上がるしぶきの強烈さは、なんともいいようがありません。
 途中、深浦で待ち合わせのためしばらく停車しますが、昨日は鰺ヶ沢に泊まりましたが、魚はこの季節、やはりおいいしいです。今朝は宿を早く出て、近所の物産センターに行ったり、元小結の舞の海の博物館(というほどでもありませんが)を訪れたり。旅に出ると、どうしようもなく早起きになってしまうのが面白いですね。見知らぬ土地だと、少しでもそこで長い時間“生きた時間”を過ごそうというのは、貧乏根性なのかもしれませんが、もはや完全に習性となっています。
途中、深浦で待ち合わせのためしばらく停車しますが、昨日は鰺ヶ沢に泊まりましたが、魚はこの季節、やはりおいいしいです。今朝は宿を早く出て、近所の物産センターに行ったり、元小結の舞の海の博物館(というほどでもありませんが)を訪れたり。旅に出ると、どうしようもなく早起きになってしまうのが面白いですね。見知らぬ土地だと、少しでもそこで長い時間“生きた時間”を過ごそうというのは、貧乏根性なのかもしれませんが、もはや完全に習性となっています。
鰺ヶ沢をあとにし、木造、五所川原、弘前を経て青森まで2時間少々。どこも皆、関取が数多く輩出している町で、なじみがあります。冬の東北、それも津軽となると、外を歩くのもはばかられそうです。実際、青森についたときは大変な雪で、凍えそうでした。しかし1時間も経つと天気は一変、まるで春を思わせるような日差しになり、積もった雪がなんともまぶしく感じられました。
寒い季節はやはり寒いところに行くのがいちばん楽しいように思えます。来月はカナダ、それも北極にかなり近いところまでオーロラを観に行く予定なのですが、いまから楽しみです。