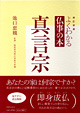福岡から東京に戻った翌7日、今度は札幌に飛びました。来年のいまごろ刊行予定の単行本の取材です。明日はまた沖縄に移動します。
沖縄・那覇に会社の分室を設けて9カ月。この間、何度も足を運びましたが、来るたびにさまざまな新しい発見があります。「時間がスローに流れる」という言葉を最近よく見聞きしますが、それを実感するのもその一つです。
クルマで走っていても、首都圏のように「急(せ)く」ドライバーのなんと少ないことか。信号が黄色だと、たいていのクルマが停車します。赤に変わっても強引に進むクルマが多い首都圏などとはまったく違います。優先権のない通りからメインの通りに出ようとするときなど、驚くほどの寛容さで道を譲ってくれます。クラクションの音もめったに耳にしません。
東京に長く暮らしていると、あわてない、急がないという暮らし方を、すっかり忘れ去ってしまっているのですが、そのことの不健全さを改めて実感するのが沖縄といっていいでしょう。
東京から来るときは、ふだんのクセというか習慣で、つい多くの仕事を持ってきます。高い送料を払って、段ボール箱にぎっしり資料を事前に送ったりもしました。ところが、那覇の空港に降り立ち、その空気に触れたとたん、仕事モードは消えてしまいリラックスモードに支配されます。そこがまた、リゾート地・沖縄の魅力なのかもしれません。
「リゾート」という言葉の語源はフランス語の“resortir”で、「再び出かける」という意味だそうです。一回こっきりで終わるのでなく、何回でもそこに行きたくなる場所──ということでしょうか。そして、その地でもう一度自分を取り戻す、もう一度自分を見つめ直す。それを実現するための空気というか土台というか、そんなパワーを秘めているのが「リゾート」なのではないかと思います。
だとすると、そういう場所に「仕事場」を設けること自体、なんだか矛盾しているような気もします。ただ、私個人についていえば、オフィスだろうが取材で出向く出張先だろうがリゾート地だろうが、そこにはいつだって「仕事」があります。どう理屈をつけようが、それから逃げることはできません。逆に言うと、どこでも、いつでもできてしまう仕事なのです。
ただし、仕事モードの中で仕事をするのと、リラックスモードの中で仕事をするのとでは、おのずと中身が違ってくるかもしれません。来るたびに「自分を取り戻し、自分を見つめ直す」ことができるのですから、心強いことこの上ないとも言えます。その強みをこれから先の仕事に生かしていきたい、そんな殊勝な(笑い)ことを思いました。