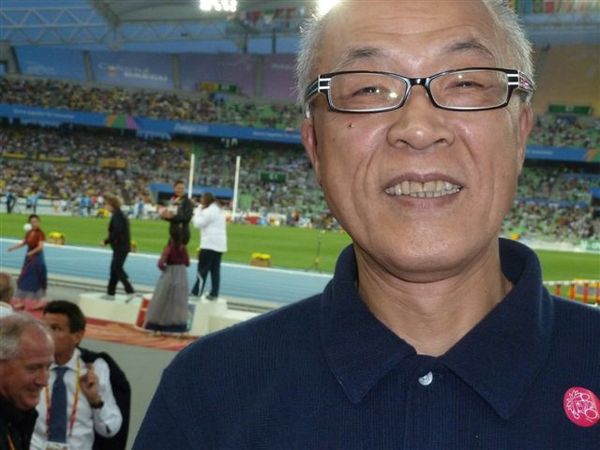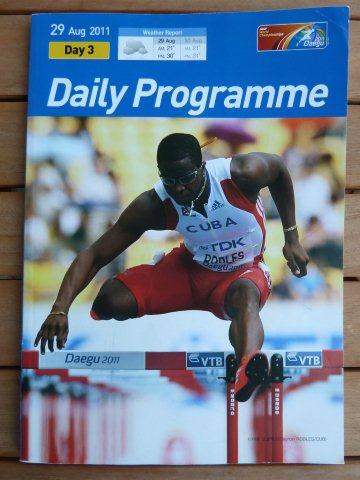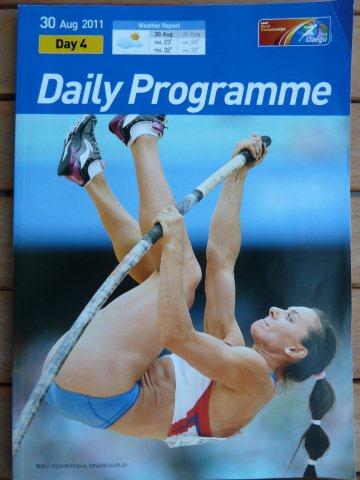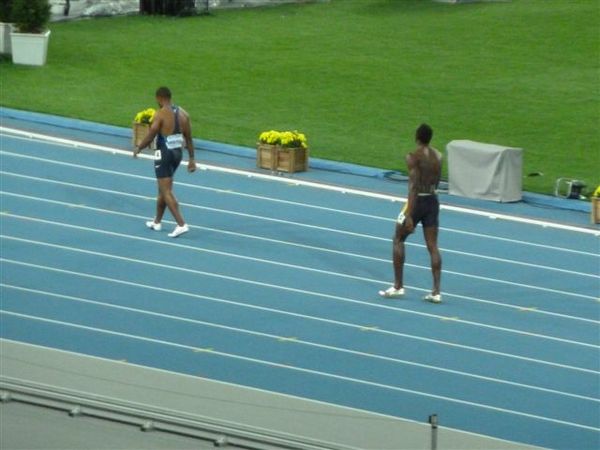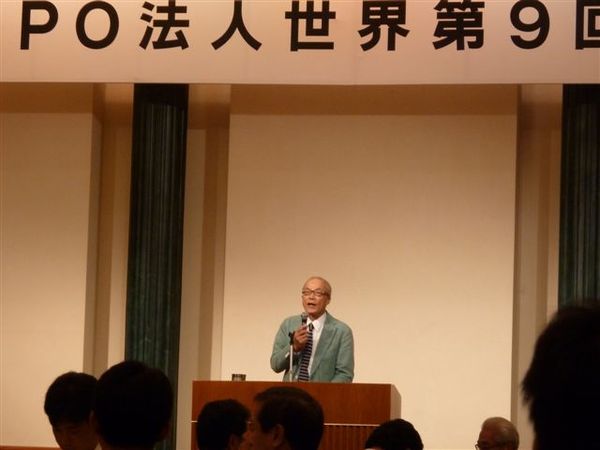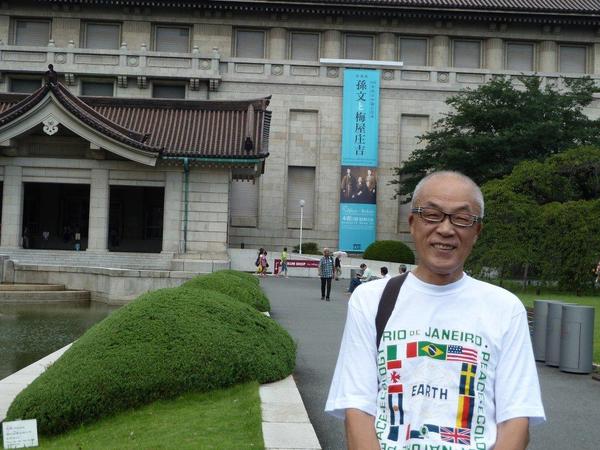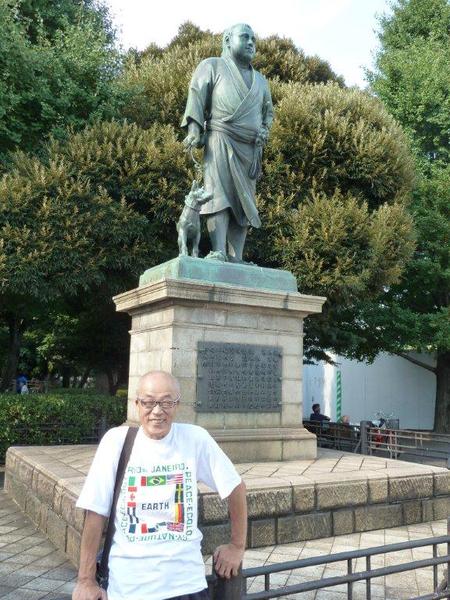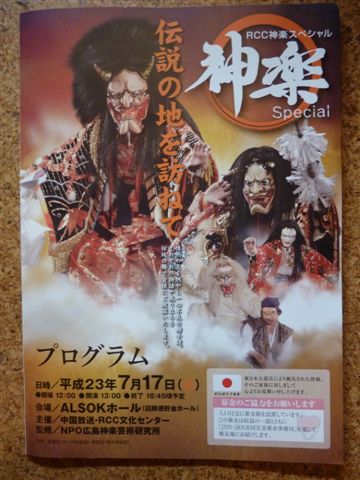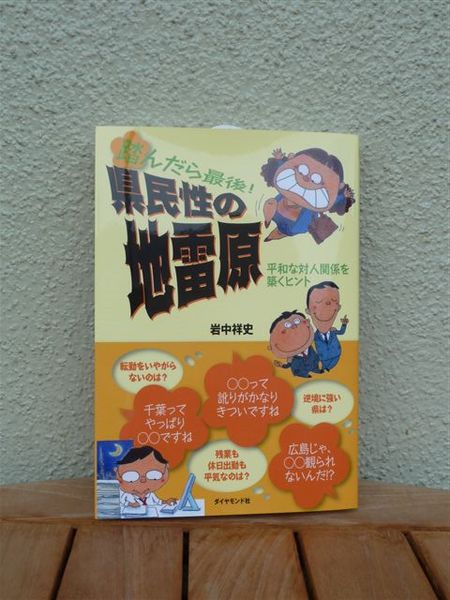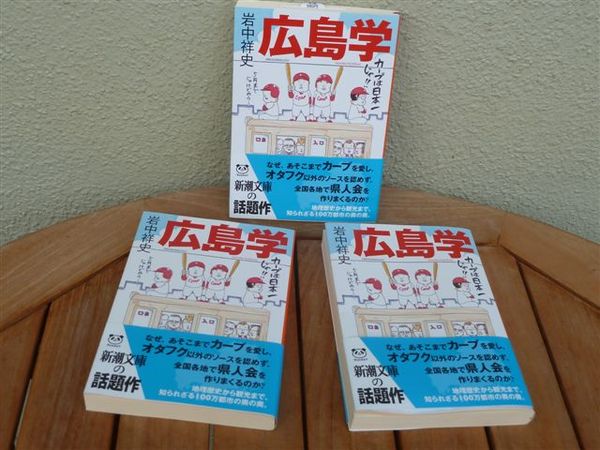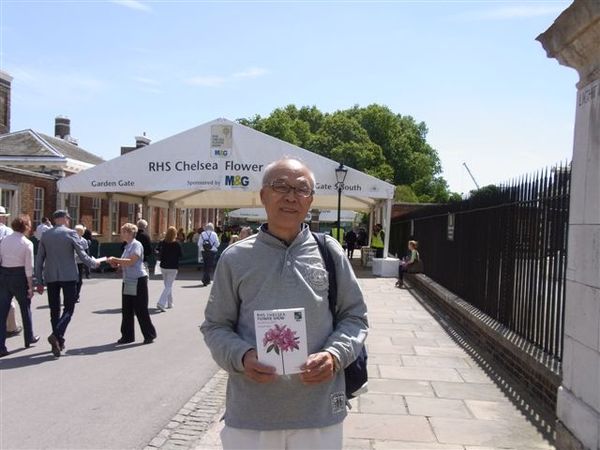2011年9月6日
韓国のエネルギーは、外国人観光客の誘致に対する姿勢にも垣間見ることができます。日本政府もいま、「VISIT JAPAN」というキャンペーンに力を入れているようです。観光庁などという役所まで設けたくらいですから、たしかに力を入れているその姿勢はよくわかります。しかし、俗にいう広告代理店ベースというか、〝お役所から予算を引っ張り出して、もっともらしいキャッチフレーズと写真を並べればそれでOK〟といった印象しかありません。泥臭い、あるいは現場ベースでの知恵が見えてこないのです。
韓国のソウルで気づいたのですが、地下鉄のホームに大きな液晶の画面が設置されていました。なんだろうと思って見ると、外国人観光客のためのガイド画面でした。ハングル(韓国語)はもちろん、英語、中国語(簡体字)、そして日本語の4カ国語の中から自分に理解できるものを選び出し、メニューに出てくる項目にタッチすると、「この駅の近くのおすすめスポット」「この駅の近くのグルメガイド」など、貴重な情報がどんどん画面に出てきます。
また、地下鉄、KORAILの自動券売機もこの4カ国語が選べるようになっています。「このボタンに触れてください」といったアナウンスも同じです。街に出ている通りの名前の表示、周辺の地図、名所旧跡の案内板など、ことごとく4カ国語の表示がなされ、これなら迷う人はいないだろうなと思いました。
東京都ないの地下鉄駅近くを歩いていると。路線地図と首っ引きで、駅の表示板をためつすがめつ見ている外国人観光客と出くわします。彼らは皆、同じことで悩んでいるにちがいありません。どうすれば○○駅に行けるのだろうかという、ごくごくシンプルな問題です。
そういえば、地下鉄車両内の路線図に出ている駅名も、ハングル、アルファベット表記、そして中国語と日本語の4つです。おもしろいのは、駅名の表記を漢字にした場合、日本語と中国語はほとんど同じなので、兼用になっていることです。この場合、表記は3種類ですむわけです。
ただ、日本語と中国語で異なる場合は、中国語が別に加わります。「プサン駅」のところには「부산역」「Busan」「釜山駅」そして「釜山站」とあります。中国語では「駅」を「站」というからです。「海雲台」は「해운대」「Haeundae」「海雲台」、そして「海云台」となっています。「云」は中国語(簡体字)で「雲」のことです。
それにしても、観光関係の仕事にたずさわる人のほとんどが日本語を苦もなく操っていることには驚きました。韓国語を話すことはハナからあきらめているこちらとしては、「では、英語で」と思って頭の中で考えていると、日本語で話しかけてきたりします。
タクシーに乗っても、運転手さんが日本語を理解していない場合は、「日本語通訳サービス」に電話がかけられます。フリーダイヤルなので助かります。運転手さん自身がかけていたこともありました。まあ、タクシーでどこかに行く場合、地名さえわかってもらえば事は足りるわけですが、その?音もこちらはあやしいわけですから、トラブルを防ぐには最善の策といえましょう。日本の観光地、とくに外国人が多く訪れるところ、また、この先たくさん来てほしいと思っているところも、これくらいの工夫が最低限必要ではないでしょうか。
あと、私が思っているのは、日本独特の食べ物の説明です。寿司やしゃぶしゃぶ、すき焼き、天ぷら、豆腐などは国際的にも認知されているので不要でしょうが、「うな重」とか「煮びたし」とか「南蛮漬け」「だし巻き卵」とか、簡単なのに、いざ説明するにはけっこう知識が求められるような日本料理がいくつもあります。観光庁あたりで音頭を取って、この種の料理の統一した英語(中国語、韓国語)訳を考案したらいいのではないかと思います。
もちろん、各お店でそれを表記するときは、ミススペルや誤記もあり得るでしょう。韓国料理の店に出ている看板やメニュ?でも、「豚の三校(?)肉」「クシ(?)パ」「う(?)―メソ(?)」「カノレ(??)ピ」といった類の誤記はしょっちゅう見かけました。でも、すぐにそれとわかりますから、さほど心配はないでしょう(でも、念のため。うーメソはラーメン! カノレビはカルビ!)。「三校肉」など、日本人でも気がつかないかもしれません(笑)。